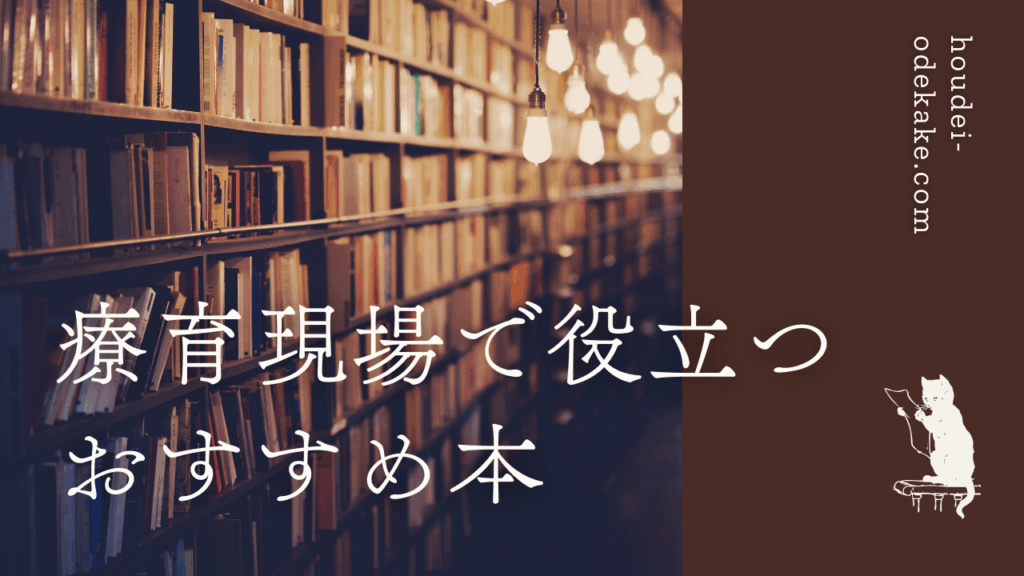
2026年1月6日更新
こんにちはmioです♪
この記事では、放課後等デイサービス職員が本気で選んだ「この1冊があれば救われる」療育の本10選を紹介します。
結論|療育の本は「読む順番」と「選び方」を間違えると、一生ムダになります
発達障害や療育の本は、
「どれを読むか」以上に「今のあなたに合っているか」 がすべてです。
- 不安なまま手当たり次第に本を買う
- 専門用語だらけで途中で読むのをやめる
- 「いいことが書いてある」で終わる
──この失敗、支援現場でも保護者でも本当に多い。
だからこの記事では
「誰が・どんな悩みのときに・どの本を買うべきか」
を明確にし、後悔しない1冊選びができる構成にしました。
【最初に確認】あなたはどのタイプ?
- 子育てに行き詰まっている
- 子どもの対応が分からず毎日がしんどい
- 療育・支援の正解が分からない
- 保護者対応や支援計画に自信がない
- 将来が不安で情報を集めている
1つでも当てはまったら、以下の本は「読む価値あり」です

放課後等デイサービスの職員として実際に現場で使用し、多くの子どもたちの成長をサポートしてきた立場から、2026年版のおすすめ療育本を10冊ご紹介します♪
どの本も、支援の現場で「すぐに使える」「子どもの理解が深まる」と評価が高いものばかり。
支援者だけでなく、発達障害を持つ方・保護者にとっても、人生を変える重要な情報満載の、『発達障害に関わるすべての人に読んでほしい本』を厳選しました。
【まず最初の1冊】『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人のための完全ガイド(著:對馬 陽一郎)
なぜこの本からなのか?
療育に関する
- 制度と支援の流れ
- 発達障害を持つ自分との向き合い方
- 家庭・学校・放デイの役割
が1冊で“地図のように”理解できるからです。
内容の要約
発達障害の症状に悩む人のために、「仕事」「人間関係」「生活」「お金」に関する具体的な解決方法に焦点を絞って解説しており、 この本で紹介する解決法は、スマホアプリを使ったものや100円ショップのアイテムでできるものなど、ちょっとした工夫で実践できるものばかりです。
当サイトでも、何度も紹介してきた『ちょっとしたことうまくいくシリーズ』が一冊の本にまとまり『完全版』として、さらに読みやすくなりました。
こんな人は”今すぐ買うべき”
保護者・放デイに入りたての職員・情報が多すぎて疲れている人・発達障害を持つ方向け(特に大人になって症状に悩まされている人)
2冊目『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ』(著:平岩 幹男)
関わり方に悩んだ時この本が刺さる
支援がうまくいかない原因は、
子どもではなく「大人の関わり方(声掛け)」にあることが多いから。
内容の要約
子どもに伝わりやすい言葉かけの工夫と、安心感を与えるコミュニケーションのヒントが満載。子どもの心に届く「声かけ」の方法が具体例とともに紹介されています。
不安定な行動や癇癪が落ち着く背景には、安心感のある言葉がけがあるというメッセージが繰り返し伝えられており、支援者が無理なく日常で使える表現や配慮が多数掲載されています。
こんな人におすすめ
保護者・支援者・放デイ職員など、子どもとの関わりに毎日イライラして自己嫌悪になってしまったり、「この対応で合ってる?」と不安な方。
3冊目:『図解でわかる 発達障害』(著:広瀬 由紀)
視覚的に学びたい人はこの本
- 基礎知識
- 支援のポイント
- ライフステージごとの制度
が分かりやすい図解で学べるからです。
内容の要約
発達障害の基礎理解から支援方法までをビジュアルで解説。初学者でもわかりやすい発達障害の基本特性から支援方法、日常場面での対応までをイラストや図解で丁寧に解説されています。
「視覚優位」「こだわり」「感覚過敏」などの特徴をどう理解し、どう対応するかが明確に書かれており、視覚的に学びたい初心者にぴったりの1冊です。
どんな人に向けて書かれているのか
支援初心者・保護者・学生向け。視覚的に理解したい方におすすめ。
4冊目:『高機能自閉症・アスペルガー障害・ADHD・LDの子のSSTの進め方』(著:田中 和代・岩佐 亜紀)
SSTの進め方に悩んでるならこれ
それぞれの特性に合わせた支援の方法を知ることができます。
内容の要約
子どもの社会性を育てるためのSSTの進め方・指導法を具体的な事例で紹介。子どもの「困った行動」の背景にある社会性の未発達を理解し、どう育てていくかを示す指南書。
実際に行われているSST活動の流れや、グループ・個別指導のやり方も具体的に紹介されており、絵カードを使った実践例なども掲載されています。
どんな人に向けて書かれているのか
放デイスタッフ・学校教員・支援者など、日々の現場で活用したい方。
5冊目:『発達障害のある子と家族が幸せになる方法』(著:原 哲也)
子育てに悩みを抱えるならこれ
今の子育てに何かしらの問題を抱え、その現状を「変えたい!」
そんな人はこの本で価値観変わります。
内容の要約
人に興味を示さない、ことばが遅い、身体の使い方がぎこちない、不器用、落ち着きがない、衝動性が高い、不注意などの子どもの発達が心配な方、
子どもの癇癪や切り替えが難しいことへの対応方法がわからない、子どもと楽しく暮らしたい、喜びを感じて暮らしたいのに、叱ってばかりで嫌になるなどの対応が分からない方を対象に、
22年間、「発達障害のある子」と「子どもと生きる家族」を支援してきた著者が、専門家としての自らの経験と学びから得た「発達障害がある子と家族が幸せになるコミュニケーションの知恵」をしぼりだした本です。
どんな人に向けて書かれているのか
子どもと家族のこれからに不安を感じている保護者。「専門家が書いた応用の効く実践書 」として関係者にもおすすめ。
6冊目:『放課後等デイサービス 5領域に対応 療育トレーニング50』(著:中村 一彰・小嶺一寿)
現場でそのまま使える
売れる理由は“使えるから”
この本は、読む本というよりは「開いて使う本」です。
内容の要約
2024年4月に実施された障害福祉サービス等報酬改定のポイントをわかりやすく解説し、事業所運営に必要な情報を提供しています。
「子どもが活動に合わせるのではなく、活動を子どもに合わせる」という理念のもと、個別支援計画におけるアセスメントの進め方や注意点が詳しく解説されており、600事業所を超える児発や放デイの先生方が、実際に実践して大好評だった療育メニューを厳選して50本書かれています。
日常の療育プログラム設計の参考になる、即実践できるガイドブックです。
どんな人に向けて書かれているのか
放課後等デイサービスや児童発達支援の現場で働く職員向け。
7冊目:『発達障害・精神疾患がある子とその家族がもらえるお金・減らせる支出』(監修:青木 聖久)
障害に関するお金の知識が手に入る
たった数千円の書籍で、一生にして数百万円~数千万円規模の支援を受けられると思うと、買わない理由は見当たらない。
内容の要約
この本は、障害者手帳の取得方法、特別児童扶養手当、障害年金、医療費助成制度など、国や自治体が提供するさまざまな経済的支援制度を紹介しています。
また、制度の利用には申請が必要であり、知らないと利用できない場合があることを強調しています。
特に、制度の存在や仕組みを知らないことで、一生利用できなくなる可能性がある制度もあるため、情報収集の重要性とそれぞれの制度の詳細が具体的に分かりやすく説明されています。
どんな人に向けて書かれているのか
主に保護者向け。支援者も仕組みを知っておくために読んだ方が良い。
8冊目:『自閉症児のための明るい療育相談室 親と教師のための楽しいABA講座』(著:奥田 健次)
少しでも療育に興味があるなら
自閉症に関わりある人なら、必ず1回は目を通して損なし。
内容の要約
著者の奥田 健次氏と小林 重雄氏は、長年にわたり自閉症児の支援に携わってきた専門家であり、その豊富な経験をもとに、応用行動分析(ABA)の実践的な手法をQ&A形式で紹介する実用書です。
全54の具体的な質問に対し、著者が独自の技法やテクニックを用いて明確な回答が提供されています。
どんな人に向けて書かれているのか
自閉症児の保護者で、日常生活での具体的な支援方法を知りたい方・ABA(応用行動分析学)の理論を学びたい支援者。
9冊目:『背景、アスペルガー先生 漫画版』(著:奥田 健次)
気持ちが折れそうなときに
ではなぜ“漫画”なのか
人は疲れているとき、文章を読めません。
それでも、知らないと始まらない。
子どもと前向きに進んでいきたいなら見るべき本の一冊です。
内容の要約
この本は、その斬新な指導法から「子育てブラックジャック」とも呼ばれる臨床心理士:奥田 健次氏が、実際のカウンセリング事例をもとに、発達障害のある子どもたちとその家族の支援の様子を描いたヒューマンドキュメントです。
原作のエピソードをマンガ化し、家庭や学校でのリアルな悩みと、それに対する斬新なアプローチを紹介しています。
どんな人に向けて書かれているのか
支援に自信を失っている・保護者の気持ちを知りたい・共感できる本が読みたい
10冊目:『発達障害の子の療育が全部わかる本』(著:原 哲也)
必ず知っておくべき”基本のキ”
療育に関する基本の知識はこの一冊で全て手に入る。
内容の要約
この本は、発達障害のある子どもを育てる保護者が、療育や支援制度について幅広く理解できるように構成された実用書です。
乳幼児期から18歳までの療育期を中心に、家庭での対応や進学・就職に関する情報までを網羅しています。
「発達障害とはなんぞや」から「発達障害のある子の就労支援」までの、生涯にわたって発達障害のある子に必要な情報が幅広く載せられ、本当にタイトル通り「1冊で全部わかる」内容となっています。
どんな人に向けて書かれているのか
保護者・療育や支援制度について知りたいと考えている方・教育や福祉の現場で支援を行っている専門職。
まとめ
療育の正解は1つではありません。
でも、「知らなかったせいで苦しむ時間」は確実に減らせます。
この中のたった1冊が、
あなたや、目の前の子ども、家族を救うかもしれません。
今回紹介した10冊は、発達障害に関わるすべてのニーズに応える内容ばかり。
支援のヒントに困ったときや、もっと子どもとの関わりを深めたいと感じたとき、ぜひ手に取ってみてください。

人生を変える有益な情報が満載で、どれも読みやすいので気になった本があれば読んでみてください♪

ここまで記事をご覧くださりありがとうございました♪
子どもの情報サイト『ほうでいなび』はこれからも
- 発達障害に関係する様々な情報
- 子どもが安心して楽しめるお出かけスポット
- お得情報やNISA活用術のようなお金の知識など
子どもと保護者に向けて、少しでも有益な情報を一人でも多くの人へ発信できるよう、心を込めて記事をつくります!
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47beba78.5015246b.47beba79.91da0ba3/?me_id=1276609&item_id=13304274&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01256%2Fbk4798188557.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4224e56c.d2383f18.4224e56d.2a505955/?me_id=1285657&item_id=11139775&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00482%2Fbk4062596849.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=21166466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0034%2F9784824300034_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4224e56c.d2383f18.4224e56d.2a505955/?me_id=1285657&item_id=10354136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00158%2Fbk4654010521.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=19270642&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8015%2F9784761408015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47d53f46.0e584df1.47d53f47.da44cae6/?me_id=1278256&item_id=24375591&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8921%2F2000016888921.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=21432847&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6485%2F9784065376485.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=13189252&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7216%2F9784761407216.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=17246230&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3466%2F9784864103466.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=20192161&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8075%2F9784065218075.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)