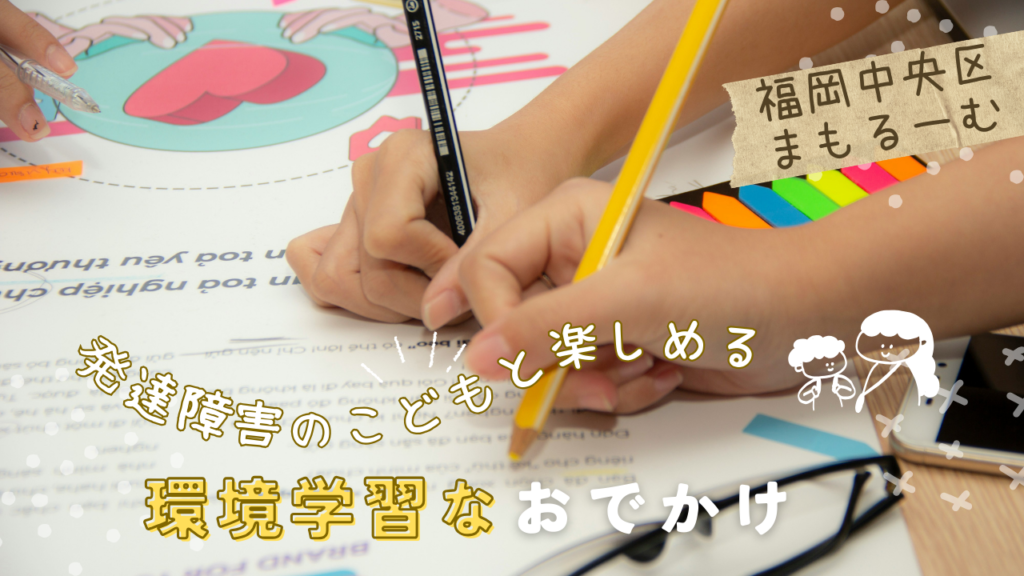
この記事の読了時間は約13分です。
こんにちはmioです。
この記事では、無料で利用できる、環境や衛生について学べる『まもるーむ』の口コミや注意点を含めて詳しくご紹介します。
発達障害児と『まもるーむ福岡』へ行くメリットと注意点
結論:まもるーむ福岡は、環境や衛生に特化した学習施設で、「見る・触る・体験する」を通じて、楽しみながら学ぶことができる学習施設です。
発達障害のあるお子さんとの外出は、目的地の選定や環境の配慮が非常に重要です。
まもるーむ福岡は、展示や体験が視覚的・体感的に学べる工夫が多く、実験や映像などで体験しながら学べる「体験学習ゾーン」と、展示物を観て自由に学べる「展示学習ゾーン」に分けられています。
そのため、それぞれの学習ゾーンごとで「ひとりの空間」の中で学べ、自分のペースで落ち着いた体験が出来るので、充実した体験・学習へと繋がります。
まもるーむ福岡に行くメリット
- 音や照明、混雑が比較的穏やかで安心感がある
- 知的好奇心を育てる「体験型展示」が豊富
- 保護者や支援者も学べる「環境×衛生」への理解促進
ただし、大きな声を出すお子さんには事前の声かけやタイムスケジュールの準備が必要です。
環境や保健衛生を学ぶことの療育的メリット
発達障害のある子どもにとって、「目に見えるかたちで物事を学ぶ」ことは、理解や定着に非常に効果的です。
まもるーむ福岡では、以下のような療育効果が期待できます。
療育との繋がり・効果
- 視覚優位の子どもに向いた展示:写真や実物、図解パネルが豊富
- ソーシャルスキルトレーニング(SST):公共マナーや順番待ちを練習できる機会
- 衛生教育:手洗いや咳エチケット、感染予防を具体的に学べる
- 環境への興味関心:生き物、気象、ごみの分別など、生活とつながるテーマ多数
さらに、「静かで落ち着いた空間」があることで、感覚過敏のある子どもでも安心して過ごしやすい構造となっています。
『まもるーむ福岡』の基本情報と施設紹介
まもるーむ福岡は、みずほPayPayドーム福岡の道路を挟んだ向かい側にあります。
主な体験内容は下記の通り。
- 衛生・環境・健康に関する体験型展示(クイズ、模型、生き物展示など)
- 定期的なワークショップや講座あり(親子参加型も)
- 視覚資料が豊富でわかりやすく、展示内容も子ども向けにやさしい表現です

さらに夏季限定で、生きている化石『カブトガニ』を見ることが出来るので、ほうでいなびでは夏季シーズンに行くことをおすすめしています!
実際に見るカブトガニは、大人でも興味津々になるほどのド迫力です^^
基本情報
- 施設住所:福岡市中央区地行浜2丁目1-34 福岡市保健環境研究所1F
- 電話番号:092-831-0669
- アクセス:
- 【電車】地下鉄「唐人町駅」徒歩約14分、PayPayドームそば
- 【バス】西鉄バス「PayPayドーム」バス停より徒歩 約4分
- 【車】駐車場については駐車台数に制限があるため事前に相談
- 営業時間:10:00~17:00
- 定 休:月曜日・火曜日(休日の場合はその直後の平日)、年末年始(12月28日~1月4日)
- 料 金:入場無料
- 対象年齢:幼児~中学生におすすめ(大人の学びにも◎)
- 公式サイト:https://www.city.fukuoka.lg.jp/m-room/index.html

駐車場はありますが、PayPayドームで開催されるライブなどのイベントがあると、渋滞で施設へ行くまでに時間がかかることもあるので、事前に調べる等の準備が必要です!
注意点:まもるーむ福岡で遊ぶ上でのお約束
発達障害のある子どもと訪れる際には、以下の点に注意しておくとより安心です。
- 静かな展示室では大きな声・走り回りはNG
- →事前に「静かなゾーンだよ」と伝えておく
- 展示物にむやみに触れないようにする
- →「見るもの・触れるもの」を事前に確認
- 混雑時は一部待ち時間が発生
- →スケジュールと「待つ練習」が必要な子には事前対策を
- 展示に飽きた場合の離脱ポイントを確認
- →事前に「ここまで見たら帰ろう」と話しておく
- 他の利用者への配慮
- →突発的な行動が出そうなときは休憩スペースへ移動

体験して終了ではなく、学びを次に活かせるようなサポートを保護者・支援者が行うことで、子どもの興味・関心や振り返りに繋がり、お出かけがより実りのある体験になるでしょう♪
まとめ:発達障害児との安全で楽しいお出かけのために
『まもるーむ福岡』は、発達障害児との療育的な外出先として非常におすすめの施設です。
事前準備を整えることで、安心して学びながら楽しい時間を過ごすことができます。
事前準備のポイント
- お子さんと一緒に「施設の写真」や「体験の流れ」を確認しておく
- 「静かなゾーン」「触れるもの・触れないもの」を一緒に練習
- 移動用のヘッドホン・飲み物・お気に入りグッズを携帯
- 長時間滞在しないスケジュールで、子どもの集中力に合わせる
おすすめの声かけ例

「次は何を見たい?」と子ども自身に選んでもらい、自己決定を促しましょう!

「ここは静かなゾーンだから、声を小さくできるかな?」と具体的に伝えるのもgood!

「もうすぐ終わるよ、最後はお魚さんを見に行こうね」など予告を忘れずに♪
子どもによって、声掛けの入りやすさなどももちろん変わります。
下記では、子どもへの上手な声掛けの仕方、関わり方、療育に対する考え方など保護者や支援者が抱える様々な問題の解決の手助けとなる本を紹介します。
お知らせ

これまで本ブログでおすすめしてきた、発達障害に関わるすべての人に読んでほしい、発達障害の人が〇〇するための本『ちょっとしたことでうまくいくシリーズ』が完全版として一冊にまとまりました‼︎
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=21432847&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6485%2F9784065376485.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/471b9d1e.27e67e5b.471b9d1f.7d4737a1/?me_id=1282686&item_id=10011801&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-funksstore%2Fcabinet%2Fch03%2Fkenkyuhakae-w_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=16696074&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6848%2F9784062596848_1_12.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42248195.b9dcb6f4.42248196.ad2af365/?me_id=1213310&item_id=21526335&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8553%2F9784798188553_1_90.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)